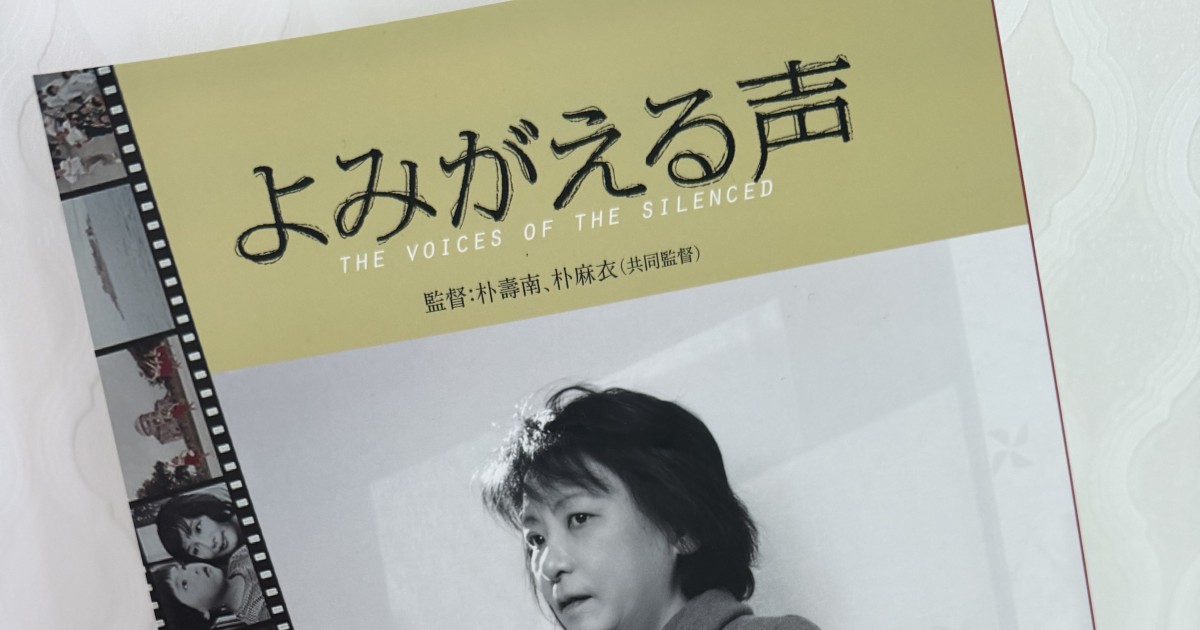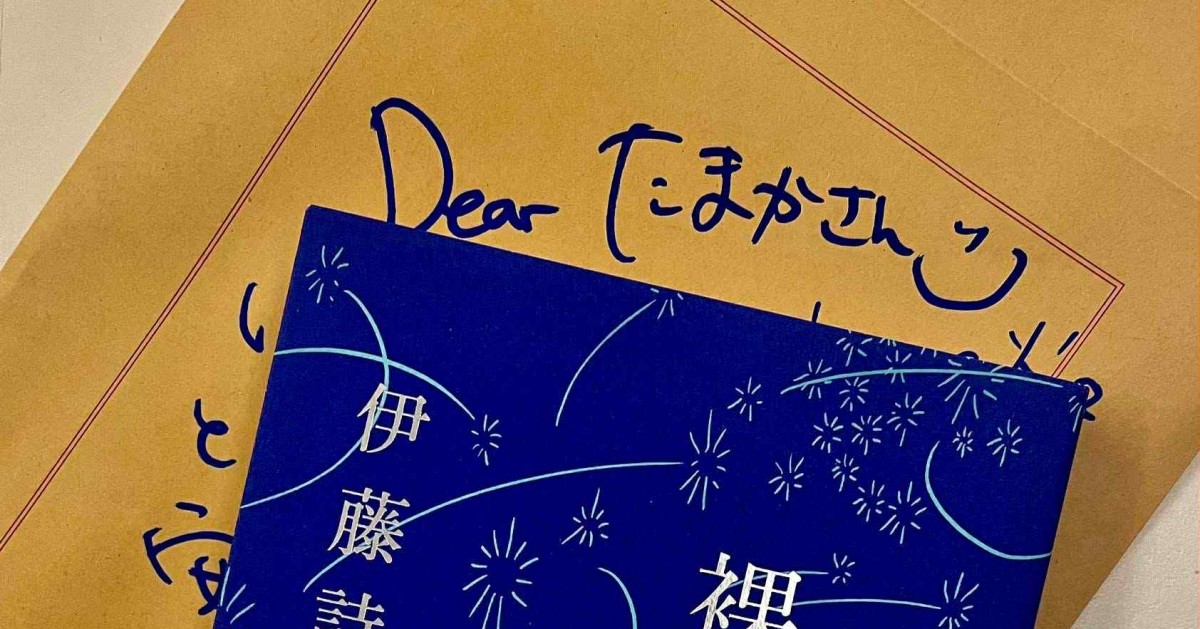たまたまな日々・個人と国家
先日も見た『戦雲』をまた見に行って来ました。京都シネマ。今回は三上智恵監督のアフタートークがあるから。
▼『戦雲(いくさふむ)』本予告篇
この予告篇が秀逸だなと思うのは、「ミサイル発射」の不穏な気配から始まり、小さな島へ自衛隊のトラックが入っていく様子が映される冒頭。そして銃声が響く。迷彩服を着た自衛隊員が「危ないですよ、道を開けてください」と住民に言い、島民の女性は見上げるようにして「道はいつでも開いてるよ、塞いだのはあんたたちじゃない。平和の道を塞いだのはあんたたちじゃない」と言う。
東京のテレビには、搬入されるミサイルの大きさも、銃声のけたたましい響きもほとんど映らない。ネット上でもそれは同じで、なぜか住民運動がエキセントリックであるとばかり強調される。
でも、実際にあのミサイルや戦車や自衛隊の隊列や訓練を間近で見て、住民運動が過激すぎると思える人がどれほどいるのだろうか。あまりにも力の大きさが違うのだが、テレビではそれが伝わっていないし、ネットではむしろ逆のようにさえ見えている。

2023年3月、石垣島の港で撮影
ミサイル搬入のための警備のものものしさ、迷彩服を着た自衛隊の訓練がさながら戦時中に見えること、無表情の威圧。全部スルーされる。

2023年3月、石垣島の港で撮影
映画の本編を見ると、与那国、石垣、宮古島あるいは沖縄本島の人々の生活や季節ごとのお祭りのシーンも多い。それだけに、その「普通」の暮らしとミサイルとのギャップにくらくらする。戦争をしないでほしいという祈りが冷笑されるようになってしまった国。

2023年3月、石垣島の自衛隊基地前で撮影
秋元康が生み出した構造を批判しようとすると、アイドル個人への批判だと誤解されることがあるのだが、自衛隊と国も同じで、国がやろうしていることを批判しようとすると、自衛隊員個人やその家族がかわいそうだという話で返される。そりゃ板挟みになる自衛隊員は、その人が善良であればあるほど苦しいだろう。ただ、個から離れて「国家権力」を象徴してしまっている事実もある。
三上監督はアフタートークで、与那国の中で島民は自衛隊と一緒に暮らしているわけだから、自衛隊に批判的と思われがちなこの映画に出演してしまうことで、その後のその人の立場がどうなるかと考えなければならなかった、という趣旨の発言をされていて、それはとても難儀なことだっただろうなと思った。ドキュメンタリー制作者としての苦しさがそのまま伝わってくるアフタートークだった。お話がうまくて終始柔和に語られるだけに逆に切実さが極まる。
誰もがみんな個と、構造に組み込まれていく一介の両方の面を持っていて、自分の意志ではどうにもならないこともある。個を傷つけずに、個を救いながら構造の変化を促すことは可能なのだろうか。
昨年の石垣島の取材については、下記記事(有料)で書きました。良かったらぜひ。
▼2023年3月18日の石垣島