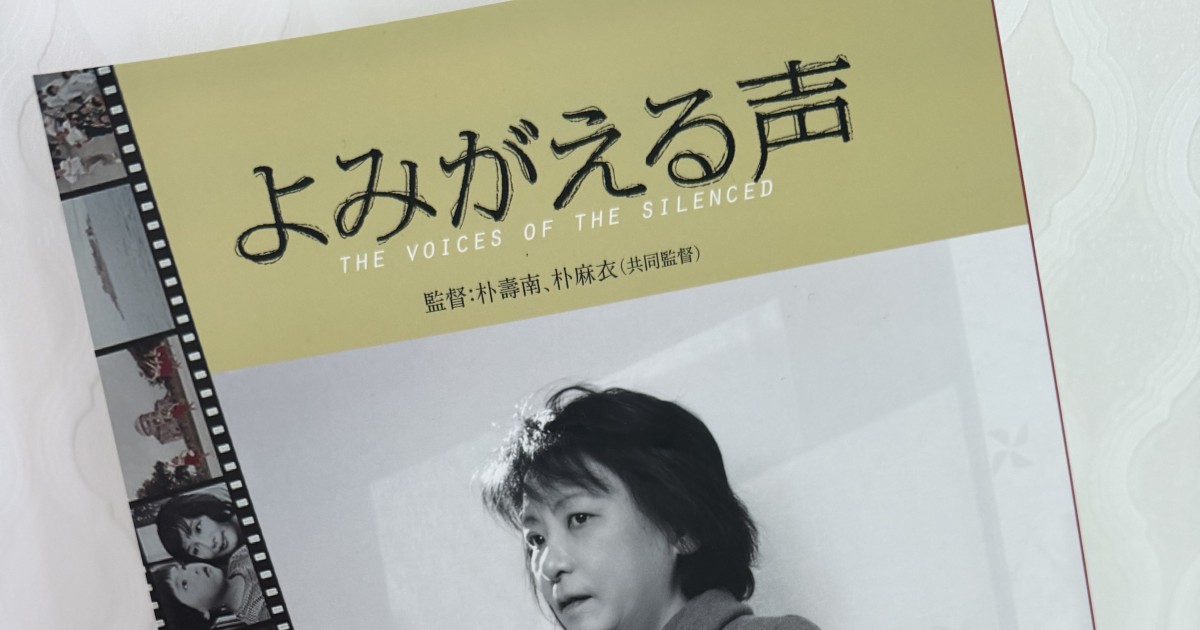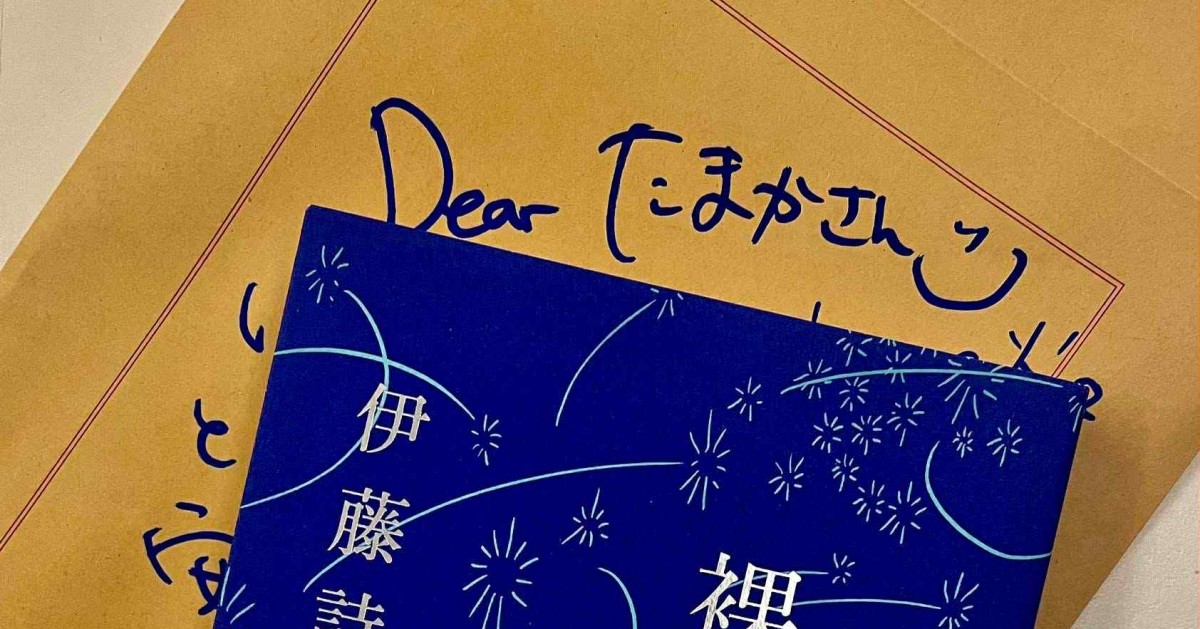たまたまな日々・映画『月』
大阪へ行って相談をして、帰ってきて映画『月』を観た日。
10月30日
本日2本目の更新です。どうしてもお昼にウートピのことを書いておきたくて、そして映画『月』の感想も今のうちに書いておきたくて。
10月30日は大阪の弁護士さんのところへ、とある事情で相談に行ってきました。ちょっといろいろとね……報告できるタイミングで書きます(匂わせ)。
映画『月』
映画『月』を見たいなと思ったのは宮沢りえ(←好き)主演で二階堂ふみ(←好き)が出ていて、「社会問題を扱う」という触れ込みの作品だったから。相模原の障害者福祉施設津久井山ゆり園での事件を扱った辺見庸の同名小説がベース。
以下、ネタバレがあります。
・
・
・
期待して見に行ったのだけどイマイチだった……。残念。
けれどどんな映画にも良いところはあるもの。最初に良いところを挙げると、「さとくん」役の磯村勇斗という役者さんがとても良かった。
事件を知っている人ならわかる通り「さとくん」は事件の犯人の植松聖であり、映画は伝えられている植松の人物像(絵が得意だったり、パーソナリティ障害が疑われる言動があったり、大麻を常用していたり)に忠実に沿った描き方をされている。
監督はおそらく、最初は(見せかけだとしても)心優しい職員だった「さとくん」がどのような心理的変化をたどって犯行を行ったか、その部分の説得力に力を入れている。磯村勇斗はその期待に応えていると思った。宮沢りえ、二階堂ふみ、オダギリジョーと磯村勇斗の4人の場面があるのだが、他の3人に引けを取らない演技をしていて見事だと思った。
二階堂ふみは『ヒミズ』の頃を思い出させる雰囲気。
・
・
・
残念な部分を書くと、結局この映画からは、「障害者」は弱く、社会の中で健常者に庇護される存在であるという視点しか受け取れないところ。
主人公の洋子(宮沢りえ)に向かってさとくん(磯村勇斗)が犯行を仄めかし、2人が言い合う場面がこの映画のハイライトなのだが、その対立は要約すると「心のない人間は人間ではないから殺していい」「それはいけないというのは偽善できれいごとでしかない」(さとくん)と、「私の言うことがきれいごとであっても私はあなたを否定する」(洋子)である。さとくんの主張を「殺人は犯罪だけど言ってることは正しい」と言い募るネットの有象無象は、洋子の言葉には説得されないだろうという感想を持った。
洋子が生まれつきの疾患を持った幼い息子を亡くし、夫(オダギリジョー)とともにその傷つきから立ち直る過程の元作家だという背景を持ってしても、彼女の言葉はさとくんの狂った熱に負けてしまっていると感じた。
それはなぜか。さとくんが前提としている「障害者にも命や生があるなんてきれいごとだ」を洋子が受け入れてしまっているように見えるのが問題だ。
障害のある人にも命がありその人生を楽しむことができるはずだというのは、きれいごとではなく真実だ。おかしいのは、障害者福祉はきれいごとだとか、本当はみんな障害者をかわいそうだと思っているはずだと決めつける思想の方だ。なぜそれを言えないのか。
障害者福祉の取材を続けるある記者は、自分は「障がい」という表記を使うことに特にこだわりを持たないと言っていた。「害」とは、障害を持つ人に向けられた漢字ではなく、現代の社会を生きる上で、社会の中にある「害」のことだと自分は思うからだと(本人がそう思っていても見た人がどう受け取るかの問題はあるけれど)。
マジョリティである健常者を標準として設計された社会は、マイノリティにとっての「害」だ。「害」があるのは、今の社会のほうだ。健常者の都合に合わせて作られた社会の中で、人は生産性で測られ、優生思想に陥ってしまう。そんな社会こそおかしいのではないか。
障害者による権利獲得運動とは、現代の価値観に抗うところから生まれている。かなり過激な運動である。資本主義への疑問にもつながる。社会の考え方を根底から変えようとしているからだ。ちなみに過激であることは悪ではない。
障害者は健常者より劣っていて、障害者は健常者のように生きたいはずだという議題設定そのものから降りなければ、ほとんどのことが「きれいごと」になってしまう。個人の「善」に頼るしかなくなってしまう。しかし映画『月』は、この議題設定の上での人間の葛藤に終始した。それが監督の描きたかったテーマであれば仕方ないけれど、私はそこから逸脱したものこそを見たかった。
ざっくりとした言い方をすれば、私たちの社会は教育や報道の中で、障害者運動の歴史をしっかりと伝えてこなかった。それが「植松聖」やその思想に共感する人を生んだ要因のひとつだと思う。そして事件に向き合うこの映画の中にも、障害者運動の視点がなかったことが残念だ。
・
・
・
映画の中で「さとくん」は、施設内の他の男性職員たちからいじめのような扱いを受けている。彼らは入所者を虐待し、園長はそれを黙認する。このような自分の扱われ方に接し、あるいは入所者の扱われ方を見て、さとくんは次第に変容していったように描かれている。
けれど問題の本質は施設の中ではなく、社会にある。洋子やさとくんの同僚である陽子(二階堂ふみ)が語る「隠蔽されている」「みんな見ようとしない」といった言葉によって、対社会がうっすらと提示されるが、この点が弱いように思った。
映し出される画面は施設の中や、洋子夫婦の家の中の様子ばかりで(そしてどちらもとても暗い)、障害者福祉施設自体を隔絶したものとして扱う「社会」の描写が薄い。社会の空気をさとくんがどう感じていたか、その点が必要だったのではないか……。
ネット上のレビューを見ていたら、「元津久井やまゆり園の職員として。」というレビューを見つけた。
↓リンク先から「クリックして本文を読む」を押すと読めます。
★1で酷評されている。
元職員の人であれば、施設や職員の描かれ方に抗議しても良いような内容だと思うけれど、レビューはそういった点よりも作品全体の出来栄えに言及している。
「総じて薄い、テーマ性の乏しい作品」というのは、私も同意。期待していただけに残念なんだ……。
また、「さとくん」の恋人が聴覚障害者で、事件当日に彼が彼女を抱きしめながら今日事件を起こすと告げる場面がある。さとくんがそう言っていることに、彼女は気づかない(口元を見ていないから気づけない)。
このレビュアーさんは「聴覚障碍者でなければ事件を防ぐことができたような表現になっていた」と書く。
さすがに監督にその意図はないと思うのだが、じゃあどういう意図だったのかがわかりづらい。聴覚障害者である彼女を欺こうとする「さとくん」の非人間性なのか。彼女には一貫して優しかった「さとくん」が、彼女には伝わらないとわかってそれを口にすることで自分の世界に閉じこもる様を表現したかったのか。
優しくて人の気持ちに敏感な聴覚障害者の女性という設定自体が、障害者や女性に対するステレオタイプなようにも感じた。都合の良いキャラクター設定。
また、このレビュアーの方は裁判などでも明らかになっていない事実があることを仄めかし、「今世に出ている事や世間が知り得ている事は裁判の証言だけで、それを料理した場合、あれが限界」という、「同席した映画監督」の話を引用している。うーんそれはどうだろうねと思う。それはいいわけではないかしら。事件についての事実を掘り下げる以外の、もっと別の視点を持ち込めたんじゃないかと。
ということで残念に思いましたが、とはいえ議論しなくてはならないテーマの映画であることは間違いなく、見に行った方がいれば感想を共有したいなと思いました。
以上です。障害者運動をもっと知りたい人におすすめなのは『差別されてる自覚はあるか: 横田弘と青い芝の会「行動綱領」』あるいは『凛として灯る』です。どちらも荒井裕樹さんの本。